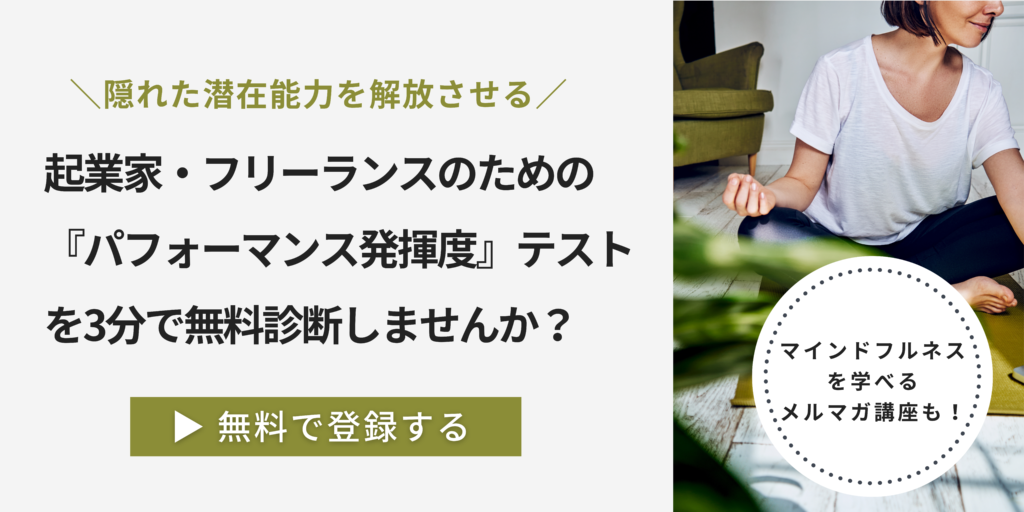注意散漫な状態が続くと、仕事もサクサク進まず、気分が下がりがちになりますよね。
集中しなきゃ、と思うのに気付くとまた気が逸れていたり…。
この注意散漫な状態を「マインドワンダリング」と呼びますが、仕事の能率を下げるだけでなく、私たちの幸福度にも深い関係があることが分かっています。
マインドワンダリングは「心の迷走」

マインドワンダリングは、直訳すると「心の迷走」。
マインドフルネスの対義語として「マインドレスネス」と言ったり、「モンキーマインド」と呼ばれたりもしますが、心ここに在らずで、目の前のことに集中ができず、次々に雑念が浮かんでくるような状態です。
そして人は、どんな行動を取っているかに関係なく、47%の割合で、今目の前で起こっていること以外のことを考えていると言われています。
1日の中で、私が「今」に一番目を向けられているなと思うのは、以前だったら朝起きてコーヒーに使うお湯を沸かしながら、朝ごはんを準備している時くらいなものでした。
起きたばかりで頭が働いていないので、余計なことを考える隙間がなかったからかもしれません。笑
徐々に頭が起きだすと、眉毛を描き足しながらこの後のスケジュールは…と考えたり、Macbookで作業をしながら、オンラインMTGが終わったら移動して、みなとみらいのブックカフェで資料を探して、○○の仕事をやろうかな。帰りは夕飯用に鶏肉買って帰ろう。と次やその次の予定を考えたり。
自分でも苦笑いしてしまうのですが、MAXで「今」に没入できそうな推しのアーティストのライブ参戦中ですら、ふと明日のことが頭をよぎったり、友達や恋人との会話の内容が勝手に頭に浮かんできたりして、ちょっとの間、今じゃない、過去や未来というバーチャルな空間に脳内だけリープしてしまうことだってありました。
これを読んでいる大半の方にもうなづいてもらえるのではと思いますが、些細なことであっても、100%目の前のことだけに集中して過ごせている時間ってかなり短いんですよね。
目の前の行動とは別のことに思考を巡らせることができるからこそ、人は計画を立てて効率的に行動したり、マルチタスクをこなせたりもするので、「マインドワンダリング」が一概に悪いことだとは言えません。
ただ、そこには1つ、重大な問題点がありました。
注意散漫と幸福度の深い関係
そもそも迷走、雑念と聞くとポジティブなイメージが浮かぶものではないですが、実際に
マインドワンダリングが発動していると、幸福度が下がる。
ということが分かっています。
参考:Matt Killingsworth,Does Mind-Wandering Make you Unhappy?,GGSCMagazine,2013
こちらのハーバード大学、マット・キングスワース博士の実証データをざっくりまとめるとこうです。
- (目の前のこと以外の)他のことを考えている場合、幸福度が大幅に減少する。
- 他のことを考えている場合、今何をしているかに関わらず、幸福度が下がる。
- 注意散漫が幸福度の低下を引き起こす(注意散漫と幸福度の低下には、強い相関関係がある)
- 不幸が注意散漫を引き起こすのでは? →相関関係は見られなかった。
「注意散漫になっている時は、心配事や不安といったネガティブなことを思い浮かべがちだから、幸福度が下がるのでは?」と考えれば、理にかなっている感じがするのですが…。
面白いのは、
「考えていることがニュートラルな(ネガでもポジでもない)ことであっても」
「現実が楽しくない時、逃避的に別のことを考えている場合であっても」
同じく幸福度が下がった、という結果が得られているところ。
目の前のことに集中できていない状態は、たとえそれがネガティブな内容でなくとも、幸福度が下がってしまうと言うから驚きですね。
ただ言われてみると、個人的にも思い当たる節はありました。
今目の前で起こっていること以外のことが、たとえポジティブな内容だったとしても…
長い時間、あるいは頻繁に目の前のこと以外の思考に邪魔をされるようであれば、仕事であってもライブ観覧中でも、集中の妨げになるには違いなく、集中できていないそんな自分にイラついてしまったり、曲に100%没頭できていないことに気がついたりして、心地の悪さを感じることが度々あったからです。
幸せな妄想をしたり、嬉しかった出来事を思い返したりすることも尊い瞬間だと思います。
だけどそればかりではなく、真剣に取り組むべきことであっても気楽に楽しみたい娯楽や食事であっても、「今目の前」で体験していることだけに意識を向ける、という時間を日常の中で長く持てることこそ、もっと尊いことなんだと、このリサーチから教えられている気がします。
マインドワンダリングは悪いことばかりじゃない?
マインドワンダリングは、DMN(デフォルト・モード・ネットワーク)という脳の神経回路が活発になっている時の状態です。
DMNは、ぼーっとしている時(=何かに集中していない時)に働きますが、以下の記事でもお伝えしたように、実は考えをまとめようまとめよう、と意識している時よりも、思考が空想の世界を彷徨っているとき=つまり、マインドワンダリング中の方が、創造性を発揮しやすいとも言われているんです。
シャワー中や散歩中に良いアイデアが浮かんできたりすることがあるのはそのためなんですね。

マインドワンダリングとマインドフルネスは対局のもの、悪と善のように語られることも多いのですが、そうではありません。
問題なのは、マインドワンダリングな状態ばかりが長く続きすぎること。
幸福度を下げたいという人はいないはずなので、努力しなくても無意識に続くマインドワンダリングな状態を、コントロールして鎮める必要があります。
ただ、どんなにリラックスしている時でも雑念はあっという間に湧いてくるように(人間の1日の思考回数は多いと6万回とも)、普通に身体を休めているだけでは、脳を休めることはできません。
脳の休息には、脳のためのアプローチをしなければならないんです。
マインドワンダリングを上手くコントロールするには

マインドフルネスには、マインドワンダリングを抑え、「目の前のことに集中する」「雑念を抑えて脳を休める」効果があり、脳科学によるメカニズムの解明もなされています。
たとえば、呼吸や筋肉の動きなど、「今自分の身体の内側・外側に起こっていること」を意識することで、過去や未来という「今以外」の場所に思考を向きにくくしていくことができます。
もし「今以外」のことが頭に浮かんできたとしても、意識を向ける対象が分かりやすいので、またすぐに「今」に戻っていけば良いだけ。
マインドワンダリングと幸福度の低下に強い関連性があるということは、「今に集中する」ことで、必然的に幸福度が高まる、ということです。
マインドフルネスを継続することで、ストレスや不安を感じる「扁桃体」の働きが抑えられたり、感情のコントロールや意思決定を行う「前頭前皮質」が発達するなど、脳の構造そのものが変化していくことも分かっています。
私自身、マインドフルネスを実践しはじめて、まず気が逸れていることに「気付く」ことができるようになりました。
マインドフルネスというものを知る前だったら、気が逸れていること自体にダメ出しをしてしまっていたのですが、そもそも「浮かんできた考えを良いもの、悪いものとジャッジしない」というポイントを学んだことで、その雑念に囚われすぎず、スムーズに目の前のことに意識を向け直す、という癖が次第についてくるように。
数値で測れるものではないですが、体感する「心の迷走」時間は格段に短くなりました。
マインドワンダリングにはメリットもあり、100%否定すべきものではないものの、脳を酷使せず休めるため、そして幸福度を高めていくためには、マインドフルネスはきっても切り離せません。
もしあなたが、ビジネスでどんなに素晴らしい結果を生み出しても、それによって十分なお金を得ていてもいまいち幸せを実感できていないなら、次はぜひ、心を満たすマインドフルネスの習慣を取り入れてみてはいかがでしょうか。