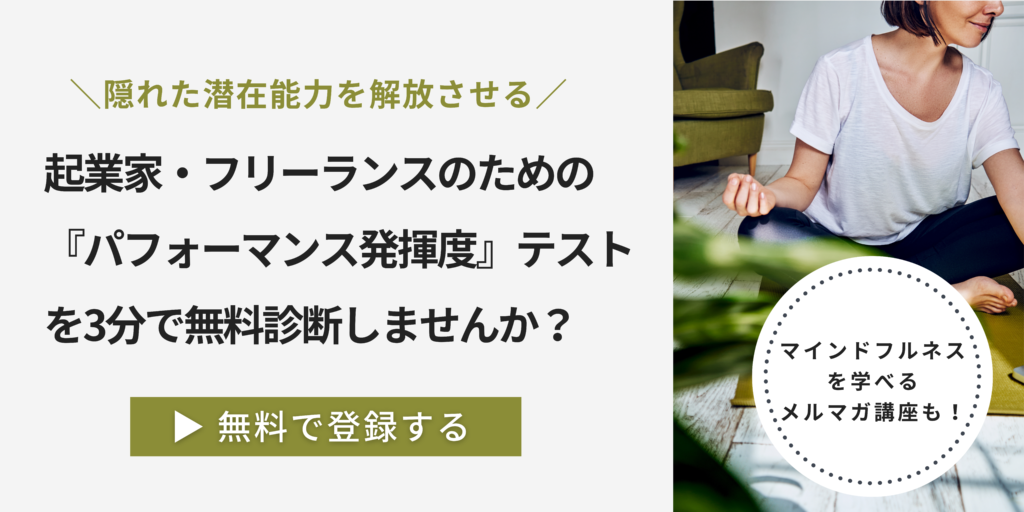マインドフルネスと聞くと、まず瞑想が一番に浮かんでくる人が多いのではないでしょうか?
確かに、瞑想はマインドフルネスのための代表的なツール(手段)ではあります。
でも、マインドフルネス=瞑想ではありません。
マインドフルネスはあくまでも「今この瞬間に目を向けている」という状態なので、この状態になれさえすれば、極論ツールはなんでも良いのです。
そこで、マインドフルネスをこれから始める方へ私が特におすすめしたいのが、動く瞑想とも呼ばれる「ヨガ」。
一見すると、美容や健康のための運動習慣、というイメージが強いかと思うのですが、それだけのものと捉えるのはすごく勿体無いです。
もちろん、今マインドフルネス瞑想だけを実践している、という方にとっても魅力的なものなので、ぜひごちらを読んで実践してみてもらえると嬉しいです。
ヨガが「動く瞑想」と言われる理由

ヨガに対する一般的なイメージは、「エクササイズの一種」というものかもしれません。
ですが、界隈では「動く瞑想」と呼ばれることも。
皆が思い浮かべる、あぐらをかいてやる瞑想、特にマインドフルネス瞑想は、呼吸や音といった何かしらの対象物に意識を向けることで「今ここ」に集中する練習をしていきます。
実はこれ、ヨガでもかなり近しいことをやっているんです。
ヨガでは基本的に、インストラクターの「吸って〜、吐いて〜」という呼吸のガイドを聞きながら、体を動かしていきます。(呼吸のガイドがある理由については、本筋とそれるのでまた別の機会に)
この「呼吸を意識する」という点は、ほとんどの瞑想と共通している部分です。
また、「背骨をゆっくりと反らして」とか、「お腹の膨みを感じて」「膝裏の伸びを味わって」など意識したい筋肉や骨の動きについても、ガイドがあるはずです。
もちろん身体自体を整えるのがメインの目的で、こういった誘導は行われているもの。
ですが、普通に生活している中では、背骨の動きや膝裏の筋肉の動きなどにイチイチ注意を向けませんよね。
意識を向ける対象が違うだけ、という話にはなるのですが、仕事や家事といった日常から離れ、ヨガを通して日頃中々しないような身体の繊細な動きに目を向けることで、自然と「今ここ」に目を向けやすくなる。
ヨガが動く瞑想と言われるのは、こうした理由からで、立派なマインドフルネスの手段の1つです。
ヨガだけやってれば、瞑想はいらない?

ヨガにもマインドフルネスの効果があるなら、ヨガだけでも良いんじゃないの?
身体にも良さそうだし。
もしくは瞑想だけでも良いのでは?
こんな風に思う方もいるんじゃないでしょうか。
当然、何もやらないよりは、ヨガオンリー、瞑想オンリーでも悪くはないです。
でも、そうではありません。
ちょっと混み入った話をすると、ヨガと瞑想は別物じゃなく、ルーツは同じ。
というか、ちゃんと勉強した人でもない限り、ヨガ=ポーズという認識が普通だと思うけど、本当は瞑想も含めて「ヨガ」と呼ぶのです。これ以上はまた話が逸れるのでやめておきます。笑
ヨガにも確かにマインドフルネスの効果はあるし、集中しよう!と無理に思わなくても、ゆっくり体を動かすことで無意識に「今ここ」に集中しやすいのはオイシイところ。
また、これはイメージ通りかもしれませんが、身体の筋バランスを整えて歪みをなくしたり、自律神経を整えたり、血液の巡りが良くなって健康になったりお肌が綺麗になったりなど…ヨガのフィジカル的な作用は計り知れません。
けれど、ことマインドフルネスという観点で言うと、やっぱり落ち着いて静かな環境でやる瞑想には敵わない、というのが個人的に感じるところです。
これはぜひ色んなマインドフルネスを試して実感して欲しい、というよりも、そうしないと分からないと思うのですが、色んな手段に触れた結果、日常におけるマインドフルネスの基礎練習として、そしてマインドフルネス自体を感じリラックスを味わうものとしても、結局瞑想こそが心地よく、最も適している手段なんだよなと実感しているからです。
例えるなら、回転が速くガヤガヤとしているカフェで本を読むよりも、落ち着いたサウンドが流れ、おひとりさまも多い静かなカフェの方がより集中しやすかったり、本を読むことに没頭できるようなもの。
うるさい方が返って集中できるんです!という方もいるかもしれませんが、多くの方にとってはきっとそうではないはずです。
かといって瞑想だけで良いか?と言うと、またそれも違います。
なぜなら、瞑想で「今」に集中しやすい状態を作るためには準備が必要だから。
瞑想も含めてヨガです、という話をしましたが、じゃあそもそもヨガの全体像って何なの?と言うと…。
ヨガにはそもそも「八支則(はっしそく)」という手順のようなものがあります。
①から始まり、⑧へと段階を踏んでいく感じです。
- ヤマ(慎むべきこと。嘘をつかない、とかNGな心構え的な話。)
- ニヤマ(心がけるべきこと。足るを知るとか、身の回りや体を清潔に保とうとか。)
- アーサナ(これがいわゆるヨガっぽいポーズ)
- プラーナヤーマ(気の流れ。≒呼吸と思ってもOK)
- プラティヤハーラ(意識を内側へ向けていくこと)
- ダーラナ(内側へ向けた意識を1点に集中させること)
- ディヤーナ(瞑想。雑念がない状態。マインドフルネスは「無」になるを目指しているわけじゃないので、微妙に意味は違う。)
- サマーディ(瞑想が極限まで深まり、一点集中しているものと一体感を感じているレベルの超すごい状態。悟りを開いているレベルとでも言ったら良いでしょうか。)
あなたは伝統的なヨガのお作法を学ぼうと思ってこれを読んでいる訳ではないと思うし、この八支則とやらを覚える必要は全然ありません(ヤマニヤマあたりは覚えておいて損はないけど)。
ただ、理屈として覚えておいて欲しいのは、「瞑想」の前にアーサナと呼ばれる「ポーズ」がある理由です。
これはそもそも、座って瞑想する習慣をつけるにあたって、瞑想しやすいフィジカル状態をキープするためだと言われています。(腰が痛かったり頭痛があったりすれば、おとなしく座って心を落ち着けるどころじゃないですよね)
最近では感度の高い人たちの間での密かなマインドフルネス瞑想ブームで、瞑想だけを実践する人も増えています。
ただ本来、瞑想は体をしっかり整えてから行うべきもの。その方がより「今ここ」に入りやすくなるからですね。
そしてそれは、ランニングや散歩といった他の運動習慣では補えず、ヨガだからこそできることでもあります。全身の筋肉や骨をバランスよく動かし、土台から身体を整えることができるのは、ヨガにしかない良さだからです。
ヨガにも瞑想にも単体の良さはあるけれど、本来は連続性のあるものだし、その方がよりマインドフルネスな状態へと向かいやすくなる。
組み合わせてやることで、相乗効果が起こり、よりその恩恵を受けられるはずですよ。
マインドフルネスの手段にもバリエーションがあっていい
マインドフルネスに向かうツールは、お伝えしてきた通り1つではありません。
ヨガも瞑想もあくまでそのなかの1つ。
日常でだって、ゆっくり散歩しながら歩いたり、周りの景色に集中したり。食事中には食べることだけに集中したり、お皿を洗ったり歯を磨いたり、1つ1つの動作に集中することで、マインドフルネスのスキルは磨けます。
ただ、日常の動作の中で意識できるマインドフルネスもとっつき易くて素晴らしいのですが、脳の構造そのものを変化させ、根本的にストレスの少ない状態を目指したり、平穏な心をキープしやすくするには、ヨガや瞑想といった、マインドフルネスの基礎練習に振り切った時間を持つことがやっぱり一番有効です。
そういった基礎練習+癒しの時間として、ヨガのポーズと瞑想を実践しながら、日常のふとした場面でもその都度実践しやすいマインドフルネスの手段を取り入れる。
このくらいの感覚で、色んなバリエーションを楽しみながら、マインドフルネスのスキルをぜひ磨いていって欲しいと思います。